
※撮影時のみマスクを外しています。
チーム医療について
チーム医療とは、一人ひとりの患者さんを中心に、様々な職種の医療スタッフが専門的な立場から関わることにより、病気の回復促進や再発の予防などを通して、医療や生活の質の向上を図るものです。
当院でもチーム医療を推進し、主治医が必要と判断したり、入院時の状況で早期の介入が望ましい場合に、チームによる支援を行います。
- NST(栄養サポート)
- 褥瘡ケア
- 緩和ケア
- ICT(感染制御)/AST(抗菌薬適正使用支援)
- 摂食嚥下ケア
- 排尿ケア
- 心不全
- 認知症ケア
- 精神科リエゾン
- 早期離床・リハビリ・栄養
- 術後疼痛管理
- 骨粗鬆症リエゾン
- RST(呼吸サポート)
NST(栄養サポート)チーム
適切な栄養管理を行い栄養改善することで、治療の効果が十分に発揮することにつながります。栄養の不足が続くことで筋力や免疫が低下し、術後の合併症や感染症のリスクが高まることがあります。
よりよい治療のために、食事・栄養剤・点滴などの栄養面の調整を、患者さんの状態に応じてサポートします。
活動内容
低栄養など栄養のサポートが必要な患者さんに、適切な栄養投与方法や内容、栄養補助食品等の提案をすることで、早期回復・早期退院のサポートを行っています。
メンバー構成
医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・薬剤師・言語聴覚士・理学療法士・臨床検査技師・歯科衛生士
褥瘡ケアチーム
褥瘡ケアチームとは
ベッド上で過ごす時間が長い患者さんに対し、褥瘡を予防します。褥瘡ができた場合には、早く治るように適切な処置を行い、悪化や再発しないように環境を整えます。
活動内容
褥瘡を有する患者さんに対し、週1回褥瘡の回診及びカンファレンスを行っています。
メンバー構成
医師・管理栄養士・看護師・薬剤師・理学療法士
緩和ケアチーム
緩和ケアチームは、患者さんのからだとこころのつらさを和らげ、快適な生活を送ることができるように専門スタッフで対応する体制を整えています。また、患者さんのご家族の精神的サポートもしています。
メンバー構成
医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・リハビリ専門職・医療ソーシャルワーカー・公認心理師・歯科衛生士
緩和ケアチームメンバーの役割
| 身体担当医師 | 痛み、吐き気、息苦しさなどのつらい身体症状を和らげる方法を考えます。 |
|---|---|
| 精神担当医師 | 心のつらさを和らげるための、カウンセリング、薬の処方をします。 |
| 看護師 | 緩和ケアに関する専門的な知識を持つ専門看護師や認定看護師がサポートします。 |
| 薬剤師 | 痛みなどの症状をやわらげるための薬についての説明やアドバイスをします。 →薬剤師からのアドバイスはこちら |
| 管理栄養士 | 食べやすい食事の調整などを通して栄養サポートを行います。 →栄養・食事のサポートについて |
| リハビリ専門員 | からだの機能や生活能力の維持、改善を目指します。 →リハビリの詳細はこちら |
| メディカルソーシャルワーカー | 金銭面や介護保険などの社会制度に関する相談に対応します。 |
| 公認心理師 | 不安などのこころのつらさへのサポートをします。 |
| 歯科衛生士 | 治療に伴う口腔トラブルへのサポートをします。 →歯科衛生士の役割について |
緩和ケアチームは、患者さんの悩みや不安について、一緒に考え、納得できる選択をするために支援していきたいと思っています。緩和ケアチームでは患者さんの苦痛スクリーニング(判定)を行っていく際にPDCAサイクルの手法を取り入れています。(P:計画 D:実施 C:評価 A:改善)
がんと診断された時から身体のつらさや気持ちのつらさを和らげる治療やケアについてのご相談は緩和ケア内科で受けることができます。
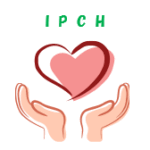
介入実績
医療用麻薬使用量
※緩和ケア介入患者のみではありません
| モルヒネ換算したオピオイド使用量推移(g) | |||||
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| モルヒネ | 内服薬 | 101 | 112 | 109 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 注射薬 | 174 | 54 | 1 | 132 | |
| オキシコドン | 内服薬 | 403 | 343 | 279 | 247 |
| 注射薬 | 48 | 31 | 77 | 67 | |
| フェンタニル | 内服薬 | 89 | 41 | 51 | 98 |
| 外用薬 | 2,412 | 1,951 | 2,070 | 2,631 | |
| 注射薬 | 648 | 791 | 706 | 746 | |
| 合計 | 3,877 | 3,324 | 3,295 | 3,953 | |
国際麻薬統制委員会(INCB)・統計のために定義された1日投与量(オキシコドン75mg=フェンタニル0.6mg=モルヒネ100mg)で換算
緩和ケアチーム介入患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 介入患者数 | 13 | 9 | 40 | 83 | 133 |
|---|
緩和ケアチーム介入患者のうち栄養介入を行った患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 管理栄養士介入患者 | ― | 9 | 23 | 21 | 45 |
| 緩和ケア(診療加算)対象患者 | 12 | 11 | 53 | 63 | 114 |
| 介入割合(%) | ― | 82 | 43 | 33 | 40 |
2020年6月から緩和ケア診療加算、2021年6月から個別栄養食事管理加算算定開始
がんリハビリテーション実施単位数(単位)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 理学療法 | 5666 | 4428 |
| 作業療法 | 274 | 326 |
| 言語聴覚療法 | 288 | 195 |
病院全体数
療法別にみたがんリハビリテーション単位数の割合(%)
| 2023年度 | 2024年度 | |
| 理学療法 | 18.0 | 15.0 |
| 作業療法 | 2.7 | 3.0 |
| 言語聴覚療法 | 6.1 | 4.0 |
| 全体 | 15.8 | ― |
病院全体数
緩和ケアチーム介入患者における口腔ケア介入数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 合計 | 8 | 5 | 6 |
| 介入割合(%) | 20 | 6 | 5 |
緩和スクリーニング実施状況(入院)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 緩和スクリーニング(STAS-J) | 7,546 | 7,669 | 6,151 | 445 |
| 新緩和スクリーニング(IPOS) | ― | ― | 1,375 | 6,295 |
| 生活のしやすさ質問票 | 71 | 97 | ― | ― |
- 2024年2月より新スクリーニングへ移行
- STAS-J、IPOS:スクリーニングの種類
- STAS-Jで苦痛が強い場合に生活のしやすさ質問票を使用
ICT(感染制御)/AST(抗菌薬適正使用支援)チーム
ICT(感染制御)チーム
病院内の感染防止対策を担うチームです。患者さんやご家族、病院で働く職員など、病院に関わるすべての人々を感染から守るために、日々活動しています。
病院内だけでなく、地域全体で感染対策が向上するよう、地域の医療機関や施設と連携し活動しています。
活動内容
- 院内をラウンドし、感染症例の把握、感染防止対策実施状況の把握と指導、抗菌薬適正使用、感染防止のための病院環境整備を実施しています。
- 医療関連感染サーベイランスを実施し、効果的な対策につなげています。
- 病院内で適切な感染対策が実践できるよう感染防止対策マニュアルを作成し、感染防止に関する指導や研修を行っています。
- 院内すべての部署から、感染防止に関する相談を、24時間受付け対応しています。
- 地域の医療施設と感染防止に関するカンファレンスを定期的に実施しています。
AST(抗菌薬適正使用支援)チーム
感染症治療において抗菌薬の適正な使用による、薬剤耐性菌の抑制、適切な治療を支援するチームです。
活動内容
- 広域抗菌薬の使用状況を把握し、培養検査結果をもとに、感染症治療の支援を行っています。
- 抗菌薬使用量・使用日数などを定期的に評価し、抗菌薬適正使用に繋げています。
- 抗菌薬使用ガイドラインを整備し、抗菌薬適正使用推進のための教育・啓発を行っています。
- 院内や他施設からの抗菌薬適正使用に関する相談対応を行っています。
メンバー構成
医師・看護師・臨床検査技師・薬剤師
摂食嚥下ケアチーム
摂食嚥下ケアチームとは
摂食嚥下(せっしょくえんげ)とは、食べ物を飲み込むことのみを指すのではなく、食べる過程全体を意味します。脳卒中、パーキンソン病などの神経筋疾患、口腔・咽頭がん、加齢など様々な理由によって食べ物を飲み込むことに障害をきたした患者さんに対して、誤嚥性肺炎や窒息だけでなく、脱水や低栄養などのリスクを回避し、安全においしく食べるための支援を行っています。
活動内容
多職種でカンファレンスを行い、患者さんの情報を共有しています(食事摂取状況、口腔内環境、栄養状態、服薬内容などの評価)。その後、ラウンドを行い、嚥下機能評価や適切な食事姿勢・食事形態を検討します。また、必要に応じ、患者さんやご家族などへ嚥下状態について説明し、食事摂取に関する指導を行っています。
メンバー構成
医師・薬剤師・管理栄養士・言語聴覚士・歯科衛生士・摂食嚥下障害看護認定看護師
排尿ケアチーム
排尿ケアチームとは
治療のために入っている尿道留置カテーテルを1日も早く抜くことで、感染症を予防します。尿道留置カテーテルを抜いた後に排尿トラブルを生じた患者さんに対し、排尿が自立できるように支援します。
活動内容
依頼のあった患者さんの病室を訪問し、チームで排尿状況の評価、治療計画の作成(患者さんに適した薬の処方、排尿しやすい下着、姿勢の工夫など)を行い、ケア実施後の評価をしています。
メンバー構成
泌尿器科医師・所定の研修を終了した看護師・理学療法士・作業療法士・薬剤師
心不全チーム
心不全チームとは
心不全の治療では、なるべく病気の悪化を抑えて、病気をコントロールしながら上手に付き合って行くことが大切です。心不全チームは心不全の治療で重要な薬物療法・食事療法・運動療法・日々の体調管理、病気だけでなく生活や社会的な支援も含め、各専門職がチーム一体となって、早期転院・退院を図りながら心不全による再入院予防や生活での困りごとのサポートをしています。また、かかりつけ医と連携し心不全治療に取り組んでいます。
活動内容
- 入院患者さんのカンファレンスを多職種(医師・看護師・理学療法士・薬剤師・管理栄養士)で行っています。患者さんの生活に合わせた再入院を予防するための方法を考えています。
- 入院している患者さんで心不全を起こすリスクの高い方のラウンドを行っています。心不全の悪化を早期に発見することや生活の中で患者さんが困っている事がないかを確認しています。
メンバー構成
医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・臨床検査技師・医療クラーク・慢性心不全看護認定看護師
認知症ケアチーム
認知症ケアチームとは
認知症によって、不安や混乱、コミュニケーションの難しさなどがみられ、その影響で治療がスムーズに進みにくいと考えられる方が対象です。
私たちは、認知症の患者さんが感じている身体のつらさや心の不安に寄り添い、少しでも安心して入院生活を過ごせるようお手伝いさせていただいてます。
活動内容
- 認知症患者さんの困り事が何かを観察し、入院生活を混乱なく過ごせるようサポートしています。また、すべての職員が認知症について正しく理解できるように、研修や啓蒙活動を行っています。
- 入院によって起こりやすい「せん妄(混乱や幻視などの症状)」を予防するための取り組みも行っています。さらに、身体拘束(患者さんの身体を縛る)をなるべくおこなわないよう、スタッフと相談したり指導を行うなど、ケアの工夫を行っています。
メンバー構成
精神科医師2名・脳神経内科医師3名・薬剤師・管理栄養士・作業療法士・医療ソーシャルワーカー・認知症看護認定看護師・精神科認定看護師
精神科リエゾンチーム
精神科リエゾンチームとは
入院生活や治療によって生じたこころのつらさに対して、医師による診察や薬の調整、専門のスタッフの面談などを行っています。他の専門職とも連携し、入院治療が安心・安全に行われるよう、お手伝いさせていただきます。
活動内容
チームカンファレンスと回診を行っています。その他にも、急な相談や困り事にも対応できるよう、相談窓口を整えています。
メンバー構成
精神科医師・公認心理師・薬剤師・作業療法士・精神科認定看護師・認知症看護認定看護師
早期離床・リハビリ・栄養チーム
早期離床・リハビリ・栄養チームとは
集中治療室において早期から離床・リハビリテーションを行う事で人工呼吸器からの離脱や入院期間の短縮などの効果が実証されています。また、集中治療開始後、48時間以内の経腸栄養開始がガイドラインで強く推奨されています。
そこで、当院では平成30年から本チームを結成し、令和1年から早期栄養介入も加えて「早期離床・リハビリテーション・栄養管理」を行っています。
活動内容
- 毎朝、チーム「医師、看護師、リハビリ専門職、管理栄養士、薬剤師、療養支援看護師、医療事務員等)でカンファレンスを行い、計画を立案しています。
- カンファレンスで決定した離床段階(ギャッジアップ座位、端座位、立位)、栄養内容などを共通の認識で実践し、状態の変化を把握しています。
- 定期的に会議を行い、手順の見直しや課題の解決を図っています。
メンバー構成
医師・看護師・リハビリ専門職・管理栄養士・薬剤師・療養支援看護師・医療事務員 等
術後疼痛管理チーム
術後疼痛管理チームとは
術後のきずの痛みは、痛みそのものがつらいだけではなく、さまざまな合併症につながるため適切に対処する必要があります。
術後の痛み治療の専門チームで、痛みだけでなく、術後の吐き気にも対応します。
活動内容
手術後1~3日目に、チームメンバーによる回診を実施しています。病室へ訪問し、痛みや吐き気についてうかがい、痛み止めの調整などを行い、少しでも苦痛を減らし、術後回復につながるよう活動しています。
メンバー構成
麻酔科医師・手術室看護師・薬剤師・臨床工学技士・医療事務
骨粗鬆症リエゾンチーム
骨粗鬆症リエゾンチームとは
脆弱性骨折(大腿骨骨折、上腕骨折など)にて入院した患者さんや骨粗鬆症による骨折リスクが高い患者さんに対して再度骨折しないように支援させて頂きます
活動内容
- 骨粗鬆症性骨折で入院した患者さんの骨粗鬆症評価(レントゲン、骨密度、骨代謝マーカー)
- 骨粗鬆症治療薬の選択・開始
- 運動療法・転倒予防の指導
- 骨粗鬆症予防の食事指導
- 口腔内清潔評価・管理
- チームカンファレンス
メンバー構成
医師・看護師・薬剤師・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士・医療事務(骨粗鬆症マネージャ-6名在籍)
RST(呼吸サポートチーム)
RST(呼吸サポートチーム)とは
人工呼吸器が装着されている患者さんに対し、各専門職が協力して、安全な呼吸の管理および早期に人工呼吸器を外せるようにサポートしています。
活動内容
人工呼吸器が装着されている患者さんに、チームメンバーによる週1回の回診を実施しています。さらに患者さんの状態に応じて、適宜対応しています。
メンバー構成
医師・理学療法士・臨床工学技士・歯科衛生士・看護師
